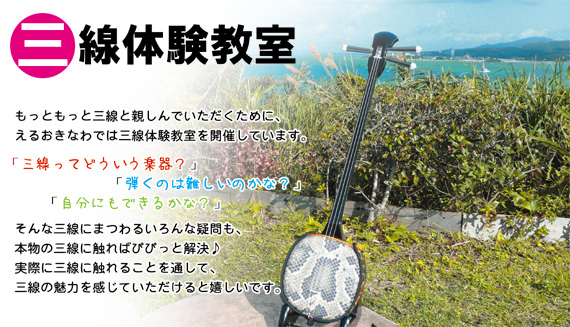2009年09月12日
波照間島「ムシャーマ」 八重山民謡のオンパレ
はいさい  がっきーです。
がっきーです。
旧盆は、縁がある波照間島で今年も行事のお手伝いをしてきました
 波照間島では、旧盆の中日(島の方言で「ナカヌピン」)に、島全体の先祖祭祀「ムシャーマ」が行われます。五穀豊穣と共同体構成員の健康への感謝の喜びを示す、古くから続く行事です。
波照間島では、旧盆の中日(島の方言で「ナカヌピン」)に、島全体の先祖祭祀「ムシャーマ」が行われます。五穀豊穣と共同体構成員の健康への感謝の喜びを示す、古くから続く行事です。
島に5つある部落を東・前・西の3組に分けた各村から行列「ミチズネー」(道揃え)が出、それぞれに衣装を着て踊りや謡いをしながら公民館まで練り歩きます。
午後に公民館横の舞台で奉納芸能が行なわれた後、夕方に再び道ズネーで部落に戻ります。
ムシャーマは国の無形民俗文化財ですが、島を出た若者が旧盆になかなか帰れなかったり、高齢化によって担い手が減っているため、集落によっては民宿に泊まっているお客さんが地域の理解を得ながら参加して行事を盛り上げるのが恒例になっています。
私は、北部落にある民宿「照島荘」や周辺の民宿のお客さんがムシャーマに参加できるためのお手伝いを毎年しています。

今年、照島荘から行列に参加したお客さんたち
ムシャーマの行列では、各演目で使われる曲が八重山民謡ファンのみなさんなら一度は聞いたことのある曲のオンパレードです 私が関わっている北部落(東組)の演目を紹介します。
私が関わっている北部落(東組)の演目を紹介します。
(写真は過去のものや他の組で同じ演目のものも掲載しています。大阪府在住の上田しょうさん、東京都在住の石丸めぐさんからもいただきました。ありがとうございました )
)

行列は、男子中学生が持つ大旗を先頭に、男子児童が持つ「ミルクナーリ」(ミルクの実、竹に実ものをいっぱいつけたもの)が続きます。ミルク=弥勒で、豊年豊漁の状態を示します。

続いて、島にユガフ(世果報=豊年豊漁の幸せな世界)をもたらすミルクさまが、大きな扇で四方に幸福を振りまきながらゆっくり歩きます。ミルクさまというのは「弥勒菩薩」から来たもののようですが、仏教的な色彩は見当たりません。後で述べる「無常念仏踊」くらいでしょうか。
ミルクさまの後には、ミルクさまが座る腰掛を持つ男子児童と、両手に粟、稲を入れたかごを持つ着物姿の女子児童が続きます。その後を、白地に赤丸の小旗を持つ子供、親子たちが歩きます。

さて、ここから謡と三線でにぎやかな行列が続きます。
演目順に見ていきます。

 行列名「みるく」
行列名「みるく」  「弥勒節」「やらよう」「シーザ踊い」
「弥勒節」「やらよう」「シーザ踊い」
 「弥勒節」 大国ぬ弥勒 我が島にいもち 御掛き欲せみしょり 島ぬ主 サンサンユヤサースリサーサー
「弥勒節」 大国ぬ弥勒 我が島にいもち 御掛き欲せみしょり 島ぬ主 サンサンユヤサースリサーサー
 「やらよう」 今日ぬ日ぬ さにしゃや ヤーラヨー ヤーラヨー
「やらよう」 今日ぬ日ぬ さにしゃや ヤーラヨー ヤーラヨー
 「しーざ踊い」 今日ぬ誇らしゃや なうにじゃなたてぃる ちぶでぃうる花ぬ ヤリクヌウネ 露ちゃたぐとぅ 遊ぶさ踊ゆさ ヨーシヌヤリクヌシー
「しーざ踊い」 今日ぬ誇らしゃや なうにじゃなたてぃる ちぶでぃうる花ぬ ヤリクヌウネ 露ちゃたぐとぅ 遊ぶさ踊ゆさ ヨーシヌヤリクヌシー
かすりをきた女性年配者(うち何人かはしめ太鼓を叩く)と地謡の男性年配者(9人が本式という)が美しいコーラスでお馴染み「弥勒節」を謡いながら歩きます。ミルク節は9番まで謡われます。おそらく、八重山古典民謡で「弥勒節」とセットになっている「やらよー」も謡われていたと思います。
行列が終わるとミルクさまを囲んで「しーざ踊い」も謡います。島のおばあちゃんたちがゆったりしたテンポで謡うその清々しさ、神々しさは、言葉にできないほど美しいものです。
この「しーざ踊い」のメロディと囃子は、琉球古典舞踊「醜童(しゅんだう)」の最後の曲「やりこのし節」とほぼ同じです。竹富島にもあるようです。


 行列名「かりゆし」
行列名「かりゆし」  「海上節」
「海上節」
 嘉利吉ぬ舟に 嘉利吉ば乗してぃ 海上穏やか 一路平安 カリユシ カリユシ
嘉利吉ぬ舟に 嘉利吉ば乗してぃ 海上穏やか 一路平安 カリユシ カリユシ
美しい衣装を付け扇を持つ女性2人と笠で踊る女児3人が扇で舞いながら歩きます。かすりもしくはワイシャツスラックスの男性地謡が謡うのは「海上節」。島で歌われるものは、八重山古典民謡のものと少し異なりますが、旅立ちを祝い航海の安全を祈る趣旨は同じです。波照間島からの旅立ちを祝う歌です。


 行列名「まみどーま」
行列名「まみどーま」  「まみどーま」
「まみどーま」
 さあまみどーま よーまみどーま 美童よ美童 ウヤキユナオレー
さあまみどーま よーまみどーま 美童よ美童 ウヤキユナオレー
原則16人で構成され、大人の男子2人が「イヤササ シーシ」と囃子を入れながらクワやビラを持って踊る人々を先導します。おなじみ八重山民謡「マミドーマ」が謡われます。

 行列名「いにすり」
行列名「いにすり」  「稲摺り節」
「稲摺り節」
 今年むぢゅくいや あん美らさゆかて 稲摺り摺り 米ゆりゆり
今年むぢゅくいや あん美らさゆかて 稲摺り摺り 米ゆりゆり
ひき臼を意味する白い布を持つ3人と、稲を持つ1人、ミジョーキー(箕)を持つ2人、杵を持つ2人、俵枡を持つ1人が、稲を脱穀するしぐさをしながら謡い歩きます。曲は沖縄本島の「稲すり節」です。

 行列名「ろくちょう」
行列名「ろくちょう」  「六調」
「六調」
 サマーヨー幾つか 二十二か三か やがて二十五の生まれ年 ヨイヤナーヨイヤサマーヨー
サマーヨー幾つか 二十二か三か やがて二十五の生まれ年 ヨイヤナーヨイヤサマーヨー
紅型ではない、和装のような無地のあでやかな着物に花笠姿の女性4人が謡い踊ります。曲は八重山民謡でおなじみ「六調」です。波照間島の唄者で奉納芸能でもメインの唄者を務める後富底周二さんが地謡をされています。


 行列名「うまむしゃ(馬舞者)」
行列名「うまむしゃ(馬舞者)」  「崎枝節(とまた節)」
「崎枝節(とまた節)」
 とぅまた松の下から 馬ば乗りおーるすや シターリユヌユバナウレ ミルクユヌタボラレ
とぅまた松の下から 馬ば乗りおーるすや シターリユヌユバナウレ ミルクユヌタボラレ
4~8人が馬の型どりを前につけて舞いながら謡い歩きます。竹富町など沖縄各地で同様の踊りがあります。那覇では、かつてあった花街「辻」の女性たちが年に一度行列をなして踊ったという「じゅり馬」が同様の馬型をつけて踊り歩きます。東組の民宿に滞在する観光客がよく参加する演目です。地謡は八重山民謡コンクールの奨励もしくは新人賞曲「崎枝節」。照島荘のサブヘルパー・ゆきこさんと私が担当しました。

 行列名「パーランク」
行列名「パーランク」
パーランク踊りであったり、ポンポン踊りであったり、その時々によります。親子で参加する場合が多いです。ここは唄三線はありません。

 行列名「くだか」
行列名「くだか」  「久高節」
「久高節」
 久高板舟乗りならてぃ マーラン高舟 舟ぬどぅんぐりしゃぬ 乗りぬならぬ
久高板舟乗りならてぃ マーラン高舟 舟ぬどぅんぐりしゃぬ 乗りぬならぬ
バソー(芭蕉風の着物)か絣着物姿の3人が、エーク(舟の櫂)を持って踊ります。
曲は八重山古典の「久高節」です。エイサーで使われる「久高(まんじゅう主)」ではありません。
このあと、波照間伝統芸能「ボー(棒)」「テーク(太鼓)」が続きます。
「テーク」では、笛の合奏に伴って打ち手と持ち手に分かれた太鼓の演舞があるのですが、京都の祇園祭の四条傘鉾が笛の音色といい太鼓といい似ていたので驚いたことがあります。室町時代の京都の芸能が沖縄にも及んでいることから、関係があるのかもしれません。


 行列名「ニンブチャー」
行列名「ニンブチャー」  「無蔵念仏踊い親ぬ御蔭」
「無蔵念仏踊い親ぬ御蔭」
行列が終わると、参加者で全員で輪踊り「ニンブチャー」を踊ります。踊りの前半はしゃがんでウサギ跳びのように1拍ずつ跳ねながら回り、後半は立ち上がって右手の手ぬぐいで左手を打ちながら回ります。
曲は「無常念仏踊い親ぬ御蔭」で、踊る者は「サーハーリヌユイサー サーサーサースリサーサー」を一緒に囃します。八重山古典民謡の工工四に載っているものとは異なり、波照間島独自のものです。室町時代に京都から沖縄に伝わった念仏踊りの名残を感じます。沖縄本島のエイサーの原型ともいえるでしょうか。
この謡は盆以外に謡うとあの世の者が間違ってこの世に帰ってきてしまうので、他の日に練習ができないとか。中央で古老が清めの酒や塩とともに歌詞や工工四を見ながら弾き謡います。
今年は我が家も沖縄戦禍をくぐって生きてきたおばあちゃんが亡くなったので、ちょっと万感の思いで加わりました。
行列は各部落から中央への往復と、部落内を1周する計3回、日が暮れるころまで練り歩かれます。島のばあちゃんによると、ムシャーマの行列は農年豊漁そして恵みの雨を祈る行事であるとともに、古くからの波照間島の歴史や豊かさ、人々の生活をを絵巻のように示してきたものだそうです。
午後に公民館で行われる奉納舞踊でも、「赤馬節」「高那節」「まるまぶんさん」「月夜浜節」といった八重山古典のスタンダードナンバーから「波照間島節」「波照間口説」「祖平花節」「五月雨節」など波照間島の民謡まで、後冨底周二さんなど島の唄者の生唄でのすばらしい舞台を見ることができます。CDで耳だけで聞くのではなく5感で音楽を体得する感じで、三線を学ばれる方にはとても勉強になるはず。
みなさんも来年の旧盆はぜひ波照間島で、参加してみてはいかが?

「うまむしゃ」前夜の練習風景
 民宿「照島荘」
民宿「照島荘」
八重山郡竹富町字波照間
TEL 0980-85-8224
 がっきーです。
がっきーです。旧盆は、縁がある波照間島で今年も行事のお手伝いをしてきました

 波照間島では、旧盆の中日(島の方言で「ナカヌピン」)に、島全体の先祖祭祀「ムシャーマ」が行われます。五穀豊穣と共同体構成員の健康への感謝の喜びを示す、古くから続く行事です。
波照間島では、旧盆の中日(島の方言で「ナカヌピン」)に、島全体の先祖祭祀「ムシャーマ」が行われます。五穀豊穣と共同体構成員の健康への感謝の喜びを示す、古くから続く行事です。島に5つある部落を東・前・西の3組に分けた各村から行列「ミチズネー」(道揃え)が出、それぞれに衣装を着て踊りや謡いをしながら公民館まで練り歩きます。
午後に公民館横の舞台で奉納芸能が行なわれた後、夕方に再び道ズネーで部落に戻ります。
ムシャーマは国の無形民俗文化財ですが、島を出た若者が旧盆になかなか帰れなかったり、高齢化によって担い手が減っているため、集落によっては民宿に泊まっているお客さんが地域の理解を得ながら参加して行事を盛り上げるのが恒例になっています。
私は、北部落にある民宿「照島荘」や周辺の民宿のお客さんがムシャーマに参加できるためのお手伝いを毎年しています。

今年、照島荘から行列に参加したお客さんたち
ムシャーマの行列では、各演目で使われる曲が八重山民謡ファンのみなさんなら一度は聞いたことのある曲のオンパレードです
 私が関わっている北部落(東組)の演目を紹介します。
私が関わっている北部落(東組)の演目を紹介します。(写真は過去のものや他の組で同じ演目のものも掲載しています。大阪府在住の上田しょうさん、東京都在住の石丸めぐさんからもいただきました。ありがとうございました
 )
)
行列は、男子中学生が持つ大旗を先頭に、男子児童が持つ「ミルクナーリ」(ミルクの実、竹に実ものをいっぱいつけたもの)が続きます。ミルク=弥勒で、豊年豊漁の状態を示します。
続いて、島にユガフ(世果報=豊年豊漁の幸せな世界)をもたらすミルクさまが、大きな扇で四方に幸福を振りまきながらゆっくり歩きます。ミルクさまというのは「弥勒菩薩」から来たもののようですが、仏教的な色彩は見当たりません。後で述べる「無常念仏踊」くらいでしょうか。
ミルクさまの後には、ミルクさまが座る腰掛を持つ男子児童と、両手に粟、稲を入れたかごを持つ着物姿の女子児童が続きます。その後を、白地に赤丸の小旗を持つ子供、親子たちが歩きます。
さて、ここから謡と三線でにぎやかな行列が続きます。
演目順に見ていきます。

 行列名「みるく」
行列名「みるく」  「弥勒節」「やらよう」「シーザ踊い」
「弥勒節」「やらよう」「シーザ踊い」 「弥勒節」 大国ぬ弥勒 我が島にいもち 御掛き欲せみしょり 島ぬ主 サンサンユヤサースリサーサー
「弥勒節」 大国ぬ弥勒 我が島にいもち 御掛き欲せみしょり 島ぬ主 サンサンユヤサースリサーサー 「やらよう」 今日ぬ日ぬ さにしゃや ヤーラヨー ヤーラヨー
「やらよう」 今日ぬ日ぬ さにしゃや ヤーラヨー ヤーラヨー 「しーざ踊い」 今日ぬ誇らしゃや なうにじゃなたてぃる ちぶでぃうる花ぬ ヤリクヌウネ 露ちゃたぐとぅ 遊ぶさ踊ゆさ ヨーシヌヤリクヌシー
「しーざ踊い」 今日ぬ誇らしゃや なうにじゃなたてぃる ちぶでぃうる花ぬ ヤリクヌウネ 露ちゃたぐとぅ 遊ぶさ踊ゆさ ヨーシヌヤリクヌシーかすりをきた女性年配者(うち何人かはしめ太鼓を叩く)と地謡の男性年配者(9人が本式という)が美しいコーラスでお馴染み「弥勒節」を謡いながら歩きます。ミルク節は9番まで謡われます。おそらく、八重山古典民謡で「弥勒節」とセットになっている「やらよー」も謡われていたと思います。
行列が終わるとミルクさまを囲んで「しーざ踊い」も謡います。島のおばあちゃんたちがゆったりしたテンポで謡うその清々しさ、神々しさは、言葉にできないほど美しいものです。
この「しーざ踊い」のメロディと囃子は、琉球古典舞踊「醜童(しゅんだう)」の最後の曲「やりこのし節」とほぼ同じです。竹富島にもあるようです。


 行列名「かりゆし」
行列名「かりゆし」  「海上節」
「海上節」 嘉利吉ぬ舟に 嘉利吉ば乗してぃ 海上穏やか 一路平安 カリユシ カリユシ
嘉利吉ぬ舟に 嘉利吉ば乗してぃ 海上穏やか 一路平安 カリユシ カリユシ美しい衣装を付け扇を持つ女性2人と笠で踊る女児3人が扇で舞いながら歩きます。かすりもしくはワイシャツスラックスの男性地謡が謡うのは「海上節」。島で歌われるものは、八重山古典民謡のものと少し異なりますが、旅立ちを祝い航海の安全を祈る趣旨は同じです。波照間島からの旅立ちを祝う歌です。


 行列名「まみどーま」
行列名「まみどーま」  「まみどーま」
「まみどーま」 さあまみどーま よーまみどーま 美童よ美童 ウヤキユナオレー
さあまみどーま よーまみどーま 美童よ美童 ウヤキユナオレー原則16人で構成され、大人の男子2人が「イヤササ シーシ」と囃子を入れながらクワやビラを持って踊る人々を先導します。おなじみ八重山民謡「マミドーマ」が謡われます。
 行列名「いにすり」
行列名「いにすり」  「稲摺り節」
「稲摺り節」 今年むぢゅくいや あん美らさゆかて 稲摺り摺り 米ゆりゆり
今年むぢゅくいや あん美らさゆかて 稲摺り摺り 米ゆりゆりひき臼を意味する白い布を持つ3人と、稲を持つ1人、ミジョーキー(箕)を持つ2人、杵を持つ2人、俵枡を持つ1人が、稲を脱穀するしぐさをしながら謡い歩きます。曲は沖縄本島の「稲すり節」です。

 行列名「ろくちょう」
行列名「ろくちょう」  「六調」
「六調」 サマーヨー幾つか 二十二か三か やがて二十五の生まれ年 ヨイヤナーヨイヤサマーヨー
サマーヨー幾つか 二十二か三か やがて二十五の生まれ年 ヨイヤナーヨイヤサマーヨー 紅型ではない、和装のような無地のあでやかな着物に花笠姿の女性4人が謡い踊ります。曲は八重山民謡でおなじみ「六調」です。波照間島の唄者で奉納芸能でもメインの唄者を務める後富底周二さんが地謡をされています。


 行列名「うまむしゃ(馬舞者)」
行列名「うまむしゃ(馬舞者)」  「崎枝節(とまた節)」
「崎枝節(とまた節)」 とぅまた松の下から 馬ば乗りおーるすや シターリユヌユバナウレ ミルクユヌタボラレ
とぅまた松の下から 馬ば乗りおーるすや シターリユヌユバナウレ ミルクユヌタボラレ4~8人が馬の型どりを前につけて舞いながら謡い歩きます。竹富町など沖縄各地で同様の踊りがあります。那覇では、かつてあった花街「辻」の女性たちが年に一度行列をなして踊ったという「じゅり馬」が同様の馬型をつけて踊り歩きます。東組の民宿に滞在する観光客がよく参加する演目です。地謡は八重山民謡コンクールの奨励もしくは新人賞曲「崎枝節」。照島荘のサブヘルパー・ゆきこさんと私が担当しました。

 行列名「パーランク」
行列名「パーランク」パーランク踊りであったり、ポンポン踊りであったり、その時々によります。親子で参加する場合が多いです。ここは唄三線はありません。

 行列名「くだか」
行列名「くだか」  「久高節」
「久高節」 久高板舟乗りならてぃ マーラン高舟 舟ぬどぅんぐりしゃぬ 乗りぬならぬ
久高板舟乗りならてぃ マーラン高舟 舟ぬどぅんぐりしゃぬ 乗りぬならぬバソー(芭蕉風の着物)か絣着物姿の3人が、エーク(舟の櫂)を持って踊ります。
曲は八重山古典の「久高節」です。エイサーで使われる「久高(まんじゅう主)」ではありません。
このあと、波照間伝統芸能「ボー(棒)」「テーク(太鼓)」が続きます。
「テーク」では、笛の合奏に伴って打ち手と持ち手に分かれた太鼓の演舞があるのですが、京都の祇園祭の四条傘鉾が笛の音色といい太鼓といい似ていたので驚いたことがあります。室町時代の京都の芸能が沖縄にも及んでいることから、関係があるのかもしれません。


 行列名「ニンブチャー」
行列名「ニンブチャー」  「無蔵念仏踊い親ぬ御蔭」
「無蔵念仏踊い親ぬ御蔭」行列が終わると、参加者で全員で輪踊り「ニンブチャー」を踊ります。踊りの前半はしゃがんでウサギ跳びのように1拍ずつ跳ねながら回り、後半は立ち上がって右手の手ぬぐいで左手を打ちながら回ります。
曲は「無常念仏踊い親ぬ御蔭」で、踊る者は「サーハーリヌユイサー サーサーサースリサーサー」を一緒に囃します。八重山古典民謡の工工四に載っているものとは異なり、波照間島独自のものです。室町時代に京都から沖縄に伝わった念仏踊りの名残を感じます。沖縄本島のエイサーの原型ともいえるでしょうか。
この謡は盆以外に謡うとあの世の者が間違ってこの世に帰ってきてしまうので、他の日に練習ができないとか。中央で古老が清めの酒や塩とともに歌詞や工工四を見ながら弾き謡います。
今年は我が家も沖縄戦禍をくぐって生きてきたおばあちゃんが亡くなったので、ちょっと万感の思いで加わりました。
行列は各部落から中央への往復と、部落内を1周する計3回、日が暮れるころまで練り歩かれます。島のばあちゃんによると、ムシャーマの行列は農年豊漁そして恵みの雨を祈る行事であるとともに、古くからの波照間島の歴史や豊かさ、人々の生活をを絵巻のように示してきたものだそうです。
午後に公民館で行われる奉納舞踊でも、「赤馬節」「高那節」「まるまぶんさん」「月夜浜節」といった八重山古典のスタンダードナンバーから「波照間島節」「波照間口説」「祖平花節」「五月雨節」など波照間島の民謡まで、後冨底周二さんなど島の唄者の生唄でのすばらしい舞台を見ることができます。CDで耳だけで聞くのではなく5感で音楽を体得する感じで、三線を学ばれる方にはとても勉強になるはず。
みなさんも来年の旧盆はぜひ波照間島で、参加してみてはいかが?

「うまむしゃ」前夜の練習風景
 民宿「照島荘」
民宿「照島荘」八重山郡竹富町字波照間
TEL 0980-85-8224
Posted by えるおきなわ at 09:00│Comments(0)
│コラム
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。